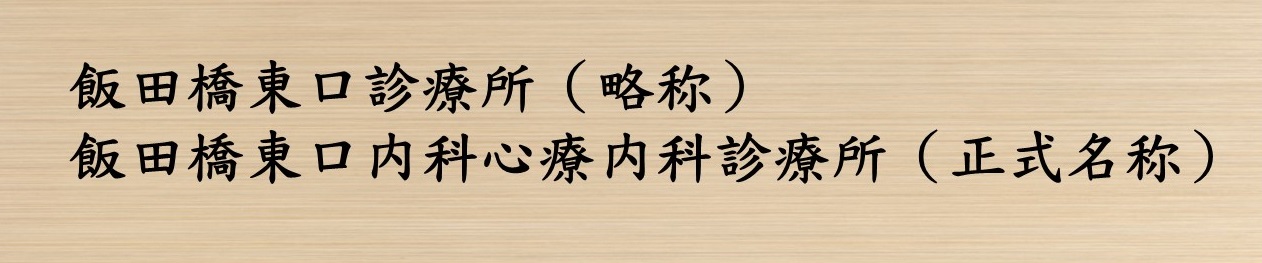
飯田橋駅東口より徒歩0分
内科・心療内科・精神科
東京都千代田区飯田橋4-9-9
第七田中ビル8階
代表電話番号:03-6874-6127
FAX:03-6260-9863
当院はJR線路沿いです
予約の仕方
予約は「初診の方へ」の頁をお読み後に診療時間内に下記にお電話ください
03-6874-6127
● 医院情報

飯田橋駅東口より徒歩0分
内科・心療内科・精神科
| 医院名等 |
|---|
| 飯田橋東口内科心療内科診療所 飯田橋東口診療所(正式略称) 医療機関コード 0134833 |
| 院長 |
| 下平 智史 |
| 住所 |
| 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-9-9 第七田中ビル8階 |
| 診療科目等 |
| 内科・心療内科・精神科 小学生以上を対象にしています。 自立支援使用可能 障害者手帳・年金記載可能 生活保護対応 |
| 連絡先 |
| 代表電話番号:03-6874-6127 FAX:03-6260-9863 救急センター・保健所・警察の公務の方専用緊急番号:070-9175-1389 業者様、患者様質問用:1@iidabashi-shinryounaika.jp |
| 補足 |
| 精神保健指定医 内科認定医 心療内科専門医・指導医 社会医学専門医・指導医 千代田区医師会員 東京大学心療内科医局員関連病院 |
医師紹介
落ち着いて穏やかに継続的な治療が大事です。
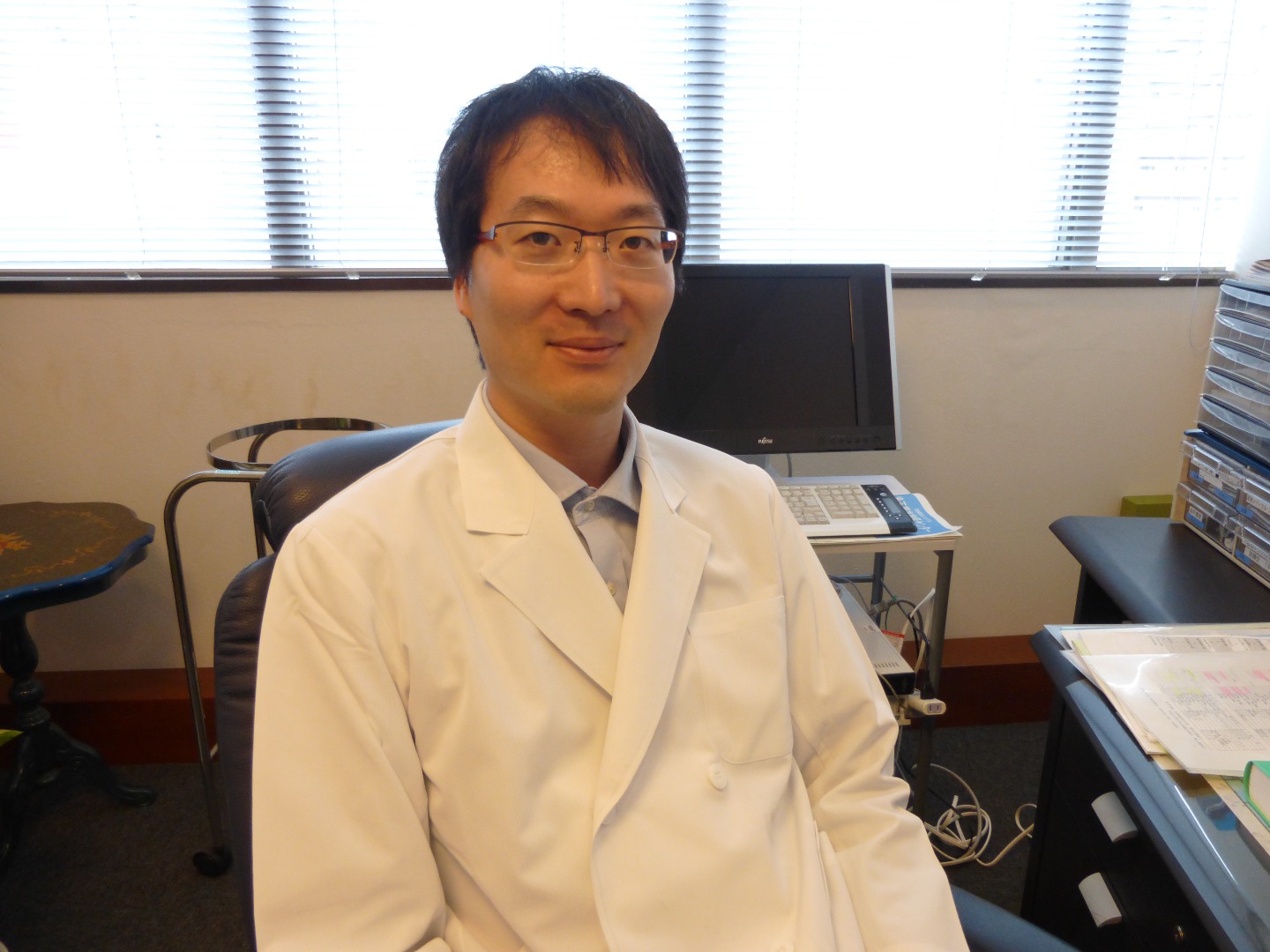
飯田橋東口内科心療内科診療所では患者さんが安心して受診できるように、常に標準的医療(ガイドライン等)を意識して、ひとりひとり異なる患者さんそれぞれの心理状態に合った最善の治療を検討したいと思っております。
会社等の休みをとらなくても通えるように夜診と土曜診療を行い、飯田橋から至近(徒歩60m)と、患者さんの負担をなるべく軽減した環境になってますので、お気軽に受診してください。
かかりつけの患者さんには風邪や湿疹や不眠、ワクチンなど、医療の心配が発生した時に安心して相談できる家庭医から、心療内科の専門医指導医をいかした医療まで提供できることを目指しております。
院長 下平 智史
職歴(一部略)
専門医歴等(一部略)
- 東京大学医学部付属病院一般内科
- 東京大学医学部付属病院心療内科
- 自動車会社・電力会社産業医
- 公立昭和病院心療内科
- 木沢記念病院
- 東京都教育委員会(復職支援)
- 長谷川病院(内科・心療内科・精神科)
- 印刷会社・人材派遣会社産業医
- IT会社・スポーツ施設産業医
- 立教大学心理学部非常勤講師
- 小川クリニック
- 元氣プラザこころの相談室
- MUFGグループ専属産業医
- 東京都の3区役所のメンタル・産業医
小児から思春期青年期をお願いしています。
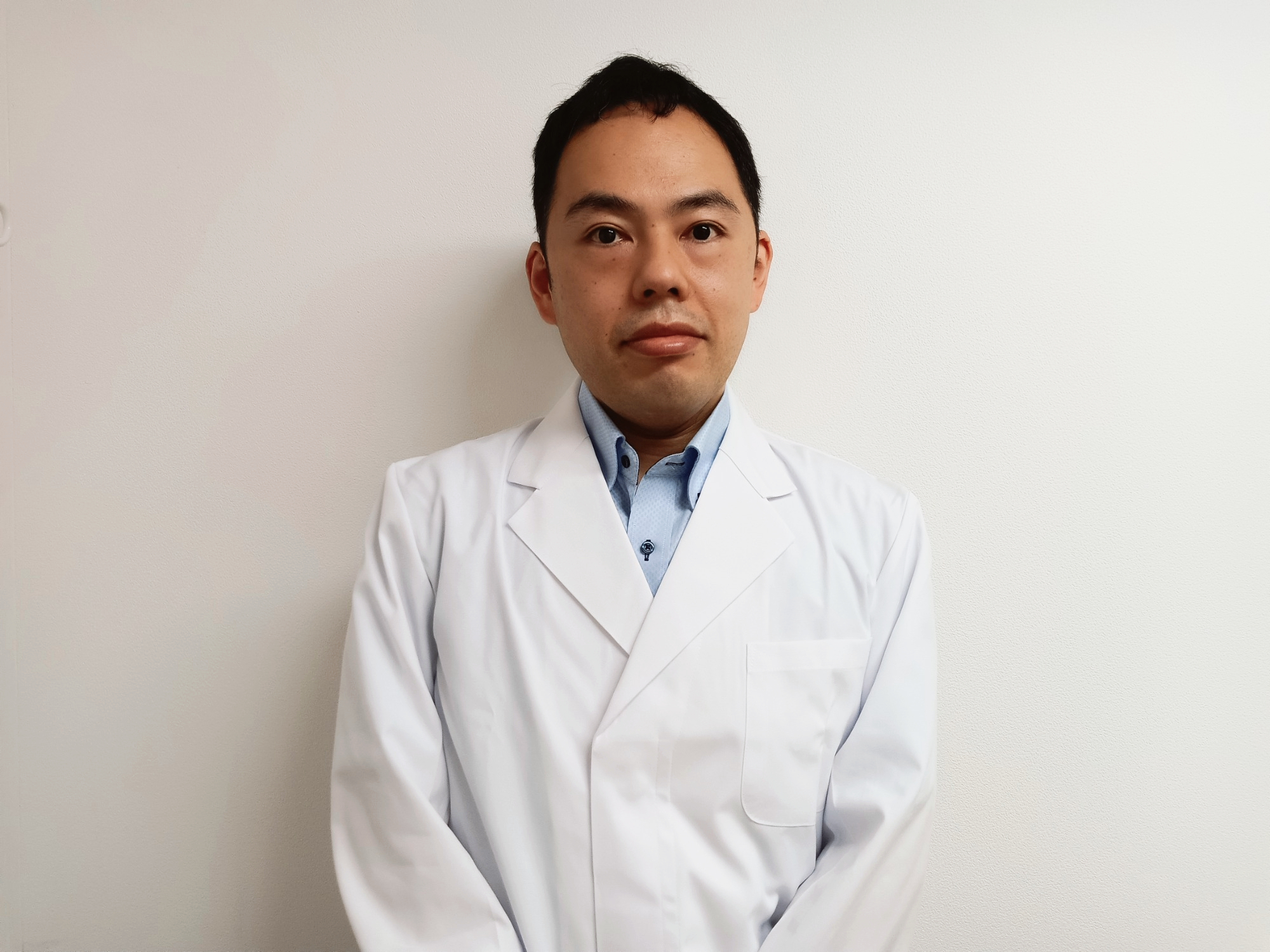
生まれ育った東京の市中病院で小児科医として勤務している小泉と申します。
小児科医として20年以上の間に様々なお子さん、ご家族と出会ってきましたが、近年、常勤施設で子どものこころ領域の診療をする機会が増えており、診療所では児童精神科を担当させていただきます。墨田区では通級利用に関するアドバイス、特別支援学級への学校訪問といった事業へ参加しております。
やや不定期で毎週ではありませんが、金曜日AMと土曜日PMに勤務しておりますので、どうぞよろしくお願い致します。
金曜午前・土曜午後 担当医師:小泉 慎也
職歴(一部略)
- 東京臨海病院小児科(現職)
- 同愛記念病院小児科
- 日本医科大学付属病院小児科
- 日本医科大学千葉北総病院小児科
- 国立病院機構 静岡医療センター小児科
専門医歴等
- 小児科専門医・指導医
- 小児神経専門医・責任指導医
- てんかん専門医・指導医
- 子どものこころ専門医・指導医(日本小児精神神経学会認定医)
- 臨床心理士・公認心理師
摂食障害と双極性障害に力を入れています。
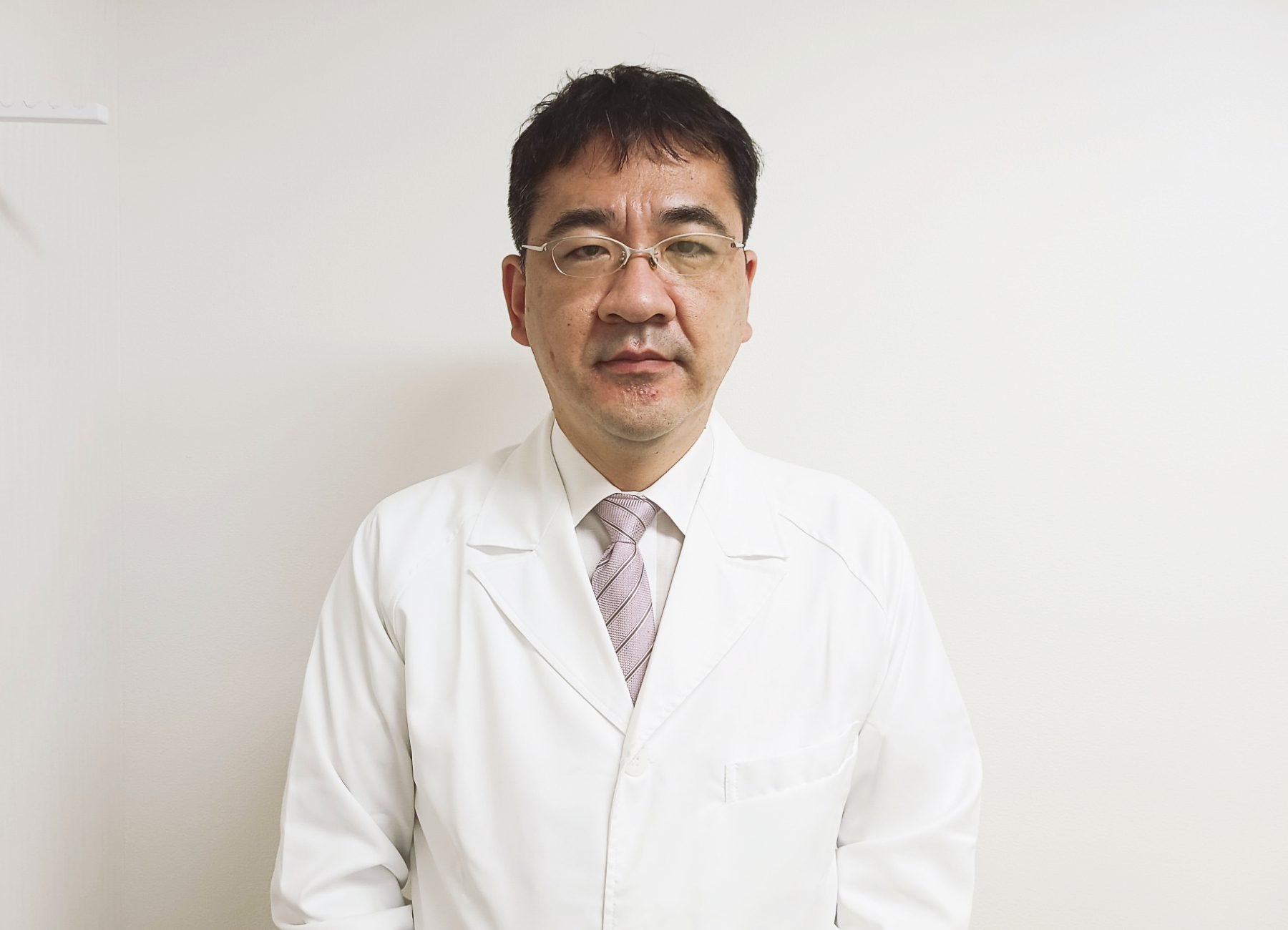
心療内科の専門医として、主に摂食障害を治療と研究に従事してきました。摂食障害以外では、双極性障害の診療を得意としています。
木曜日夜担当医師:大谷 真
職歴(一部略)
- 山王病院 心療内科部長(現職)
- 国際医療福祉大学 医学部 准教授(現職)
- 東京大学医学部附属病院 心療内科
- NTT東日本病院 心療内科・精神神経科
- 国立病院機構 花巻病院 精神科
専門医歴等
内科疾患と心療内科疾患の受診
年をとってくるにしたがって、いくつかの病気を抱えることが多くなってくるでしょう。メンタルの病気(うつや不安や不眠)と体の病気(生活習慣病)など心と体が両方関係している病気になる方も多いと思われます。
当院では両方一度にかかることが可能です。家庭医として可能な限り対応していこうと思っております。湿疹の軟膏や花粉症の目薬まで一般のかかりつけ医が対応している疾患はしっかり診ていきます。ひとつの診療所で治療が終われば、かかる費用は格段に安くなりますし、負担も少なくなるかと思います。
各専門医でないと見られない内科の重症の患者さんは近隣の病院に紹介させて頂きますが、そうでなければ専門を持った家庭医としての役目を担っていこうと思っております。
病名の告知と医療
当院は患者さんが望めばしっかりと病名を告知して、現在の状態から改善させる方針を立て、実行し患者さんのセルフケア能力を高めていける診療所でありたいと思っております。
10年以上産業医をしていると病気で数ヶ月どこかの病院に通っているにもかかわらず、何の病気ですか?どんなお薬を飲んでいますか?といった質問に適切に答えられない人があまりにも多くいるのに驚かされます。特にメンタル疾患や生活習慣病の方に多い気がします。
現在は情報化社会であり、さまざまな書物が手に入りますし、玉石混合でよければネットで情報を手に入れることができます。英語などができればその情報量は膨大なものになるかと思います。その中で患者さんが自分の病名を正確に知ることができないと、どの情報を手に入れたらいいのかがわからず、変な情報に惑わされることが多いかと思います。書物以外にも心理センターなど特に東京の人は自分の援助を受けられる機関が多々あります。
職場でも病名を知らされないと、せっかくの職場復帰プログラムがあっても適応されなかったり、職場での配慮もどうしたものか分からなくなってしまいます。
発達障害からうつ病になった患者さんのことを考えてみましょう。仕事を休まれて体調がよくなって復帰した後までを考えてみましょう。自分がうつ病になりしばらく休み、自分のことを考える余裕が出たときに、病名がしっかり伝えられている人は発達障害やうつ病の本をたくさん読むでしょう。その本からどうしたらうまくいくのかを勉強しトレーニングを積む機会もあるでしょう。人によっては発達障害センターや心理室を訪れてうつ病や発達障害のカウンセリングや治療を行うと思います。もし認知行動療法など学べば何枚も何枚も認知再構成法などを記載するでしょう。何日も何ヶ月も自立訓練法をやるかもしれません。それを見た産業医や会社は職場復帰を前向きに捕らえがちであり、復帰後にどうしたら病状が再燃しないようになるのか考え対応してくれるでしょう。もっとも大事なセルフケアをするためには病名告知が必要であると思います。
しかし、一方で病名がつげられず自律神経失調(実際は不眠や抑うつや興味の消失があるのに)とだけ言われていたらどうでしょう。自律神経失調症は自律神経が乱れているとうい状態像であるのでしっかりした医者などが記載した本は見つからないでしょう。あったとしても自律神経を整えるだけであり、抑うつ感の治療にはならないものです。一般の方が書かれた適当な本を読み、何の訓練をしたらいいか分からない状況になるでしょう。そこで、先生に「病名を教えてください。しっかり病名や改善していく対策を立ててください」といえる患者さんはいいですが、そうでない患者さんは自律神経失調症かなとおもって、そこでなにもしなくなってしまいます。これでは復帰のときに産業医はこの人は病名を理解していないな、対策もできていないな、復帰してから困難が多く再燃するだろうなと思いもっと訓練するように言うでしょう。何より疾患の改善や再発予防で最も重要なプロセスであるセルフケアができないかと思います。
メンタル疾患に限らず糖尿病であっても、「糖尿の気がある」と言葉を濁していたら糖尿病の生活改善をする機会が失われるかと思っております。しっかり診断基準に照らし合わせ、糖尿病の人には「糖尿病である」と告げて認識をしっかり持って頂き、その後その状態を改善していくにはどうしたらいいかを話し合っていけるのがいいのではないでしょうか。
(ただ、小児や認知症の患者さん希死念慮が強く落ち着いて検討できない方に関しては上記が当てはまらないかと思いますので、患者さんそれぞれにあった対応をしていきたいと思っております。)
長期処方に関して
当院は慢性疾患で1年近く現在の薬で落ち着いている方に関しては3ヶ月までの長期処方としたいと思っております。もちろん毎月受診して頂いて、体調管理をしていくのがベストであると思っております。数年飲み続けており、処方量が変更無ければ半年なども処方したこともありますが、やはり来るまで心配してしまいますので、1シーズンに一度は来てくれるつまり「3ヶ月に一度は受診するよう」にお願いします。
また、一ヶ月以上の長期処方が保険診療で認められていない薬もありますので、そういった薬においては一ヶ月までとなってしまいます。これは当院の工夫ではどうにもならないものですのでご了承ください。正月だから、海外にいくからといわれましても保険診療ではそれ以上出せないのでご理解ください。自費なら出すことも可能です。
薬の副作用への考え方(飯田橋東口内科心療内科診療所において)
投与した薬に関しては謙虚に副作用を見ていくことが大事であると思っております。よく医師と患者で「副作用だと思うのに、副作用でないと言われた」と気落ちしている方をお見受けしております。なんでも副作用と思う人もいて過剰に心配する人もいますし、医者は自分の出した薬で副作用がおきないと願いたい気持ちから否定に走るという心理状態から、患者医師関係が崩れていて私は残念に思います。飯田橋東口内科心療内科診療所では患者さんの副作用の不安にもしっかり向き合い、話し合っていける診療所でありたいと持っております。
薬は医薬品医療機器総合機構(PMDA)という厚生労働省の外郭団体の独立行政法人により副作用の内容や頻度を添付文章というものに管理記載しております(薬屋に記載をさせている?)。医師用の添付文章と患者さん用の患者向医薬品ガイドによって副作用などを見ることができます。これ以外にもPMDAからの注意喚起や警告の書類が緊急で出ることもありそれらを参考にしています。なんでも副作用と認定するのではなく、これらの情報から患者さんの状態を診察して決めていき、副作用であればその副作用がどの程度患者さんに影響を与えていくものであるか検討していき、継続か中止か、副作用を軽減する薬を出すのかなどを検討し相談していきます。また添付文章等以外でもABAB法というのが心理業界にはありまして、AをしてBが発生して一度やめてみて再びAをしてまたBが発生するということでAとBの因果関係を検討しております。(当たり前といえば当たり前ですが)ただ、当院は服薬は患者さんの同意と納得を重視していますので、患者さんがやめたいときは薬は中止にもっていきます。
では不幸にも重篤な副作用が出た場合はどうしたらよいでしょうか。薬は重篤な副作用が出る可能性がありますが、その期待値よりも改善の期待値の方が大きいので薬として認可されています。タクシーに乗る時に事故で死ぬかもしれないリスクはありますが、その期待値よりも目的地に早く着く期待値が高いため仕事として認められているのと同様です。交通事故は保険でまかなわれますが、薬の重篤な副作用は保険ではなく、PMDAにおいて薬屋と国で共同で出資して医薬品副作用救済制度というものを作っておりまして、これに患者さんが申請して重篤な副作用であれば救済を受けられるということになっております。ここで専門家による詳細な副作用認定が行われます。このシステムにより金銭的には少し安心して薬の服用ができることになります。また飯田橋東口内科心療内科診療所では民間の三井住友海上火災保険株式会社による医師賠償責任保険に加入しておりますので、この二つの保障の範囲において対応しております。医療というのは結果責任を負わず期待値や改善の可能性を追求する仕事ですが、飯田橋東口内科心療内科診療所ではこのような救済のシステムはあります(金銭的にはですが)。重篤な副作用は出始めているときに受診して診察することがもっとも大事です。最初は軽微な副作用が悪化するのかどうか最近はオンライン診療もありますので毎週確認しさせてください。時には肝臓や腎臓や皮膚科の専門の先生の力をかりながら、重篤にならないようにコントロールしていきましょう。
最近の薬は以前とは違い治験がしっかりと行われ副作用をしっかり評価しているため副作用発現率が8割ぐらいの新薬もあります。しっかり副作用を見極め、副作用の出はじめに注意してそれに対応していくのが薬とうまく付きあう方法です。不眠症,うつ病,自律神経失調,生活習慣病,高血圧,高脂血症など、どんな病気であっても自分が継続的に飲んでいる薬に関しては副作用がどんなものがあるのか、重篤な副作用として何が発生する可能性があるのかぐらいは必ず調べてくださいね。
妊娠と薬(飯田橋東口内科心療内科診療所においては)
飯田橋東口内科心療内科診療所では妊娠中はなるべく投薬を避けることが良いかと思いますが、妊娠中も仕事をする必要がある方も年々増えておりますし、必要にはなることは理解しており、下記段落のようになるべく安全な薬を積極的に使っています。
薬に対しての運転も妊娠も私は個別に判断をしていません。薬局で出される紙に運転などの危険な行動を伴う行動は注意と書いてあれば注意ですし、禁止とか入れあれば禁止です。薬のリスト上で妊娠リスクがAであればA、DであればDのリスクがあります(妊娠と薬_04-00 (okusuri110.com))。私は薬の量を少しか出さないことも多いですが、それでもそのリスクがあると認識ください。事前に運転や妊娠の希望があれば投薬変更の都度申してくださればしっかり調整します。現在、薬を過去に飲んだせいで今後の妊娠のリスクが上がるものはほとんどなく、当院で出す薬にはありませんのでので服用しているときだけのリスクです(勘違いされる人が結構多いです)。別途相談窓口も紹介してます(妊娠と薬情報センター | 国立成育医療研究センター (ncchd.go.jp))
